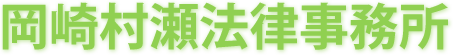- 会社の経営が厳しいが、人員整理(解雇)したい。
- 期間1年の労働契約について、次回から更新しないことにしたが、問題はないのか。
- 会社の組織を変更したことで、従業員を別会社に出向させたい。
- 個人情報を含むコンプライアンスの整備について相談したい。
- ハラスメントについて会社はどのような対策を取るべきか。
- 職場でセクハラの被害にあった。会社に損害賠償を請求できないか。
- どのような場合に労災保険の給付を受けられるのか。
- 労災保険の給付に関する処分に不服があるが、どうすればよいか。
- 残業代を払ってくれないが、会社の経営が厳しいことは理由になるのか。
- 会社が倒産した場合、賃金は払われないのか。
- クビと言われたが、従わなければいけないのか。
- 取引先から契約書が送られてきたが、契約書のチェックをしてほしい。
- 取引先との契約書を作ることになったが、どう作ってよいかわからない。
- 問題があったとき、すぐに法律相談をして、対策を立てたい。

従業員との関係について
1 始めに
会社(使用者)にとって,従業員の方の存在は,きわめて重要と言えますし,また,労働法上も会社(使用者)が雇用主である地位を濫用して従業員に対して不当な要求圧力等をかけられないよう,種々の手当てがなされています(解雇権濫用等)。
もっとも,中には,会社(使用者)の方針に会わない場合にとどまらず,却って,会社に損害を加えてしまう恐れのある従業員がいることもあろうかと思います。
その際に,会社として,毅然と対応するために,事前に,どのような備えが必要かなどは検討,準備しておく必要があります。
2 問題(例)について
就業規則上,懲戒に関する根拠規定が存しない場合でも,懲戒処分をすることはできるのか
就業規則に懲戒事由を記載したいが,内容はどの程度記載すればよいか。
懲戒処分にする際の告知はどのような方法で行えばいいか。
従業員が問題を起こしたが,就業規則の懲戒事由に当たらない。新しく懲戒事由を設けて,これを理由に,懲戒することはできるか。
懲戒処分の内容をこれまでよりも厳しくしたいが,問題はあるか。
懲戒処分には,どのような種類があるか。
従業員がインターネットに不適切な内容を書き込んだことを理由に懲戒することができるか。
従業員に始末書の提出を求めたが,提出しない。提出を強制できるか。また,提出しないことを理由に懲戒することはできるか。
従業員の私生活上問題を理由に懲戒できるか。
従業員が行った非違行為は,いつまでさかのぼって対象とすることができるか。
従業員を懲戒するにあたって,どのような手続きを与えなければならないか。
懲戒処分をするに際して,従業員に弁明の機会を必ず与えなければならないか。就業規則には弁明の機会を与えると書いていない場合はどうか。
弁明の機会を与えようとしたが,従業員が調査にも協力せず,また,弁明のための聴取にも理由なく応じない場合であっても,必ず弁明の機会の付与が必要なのか。
従業員が,弁明の機会に,第三者(家族,労働組合,代理人など)の立会を求めているが,応じなければならないか。
会社としても事情を把握するために,従業員に事情を聴きたいが,従業員が協力しない。従業員に協力することを求められるか。
従業員の会社の机を勝手に開けることができるか。
従業員の私生活について会社は調査することができるか
出勤停止、懲戒休職および懲戒停職の制度を設けたいが,可能か。どのような方法によればよいか。
出勤停止はどの程度の期間にすべきか
出勤停止の期間中の給与は支払うべきか。
従業員の給与を減給させたいと思っているが,どの程度までカットしてよいか。賞与をカットする場合と,違いはあるか。
従業員を正社員から契約社員することはできるか。
従業員を降格させて賃金が低下することとしたいが,これは減給の制裁にあたるか。
懲戒解雇したが,退職金を支給しなければならないか
従業員が懲戒処分されたことを社内で公表してよいか。
社外の人から従業員の懲戒の有無等の聞合せが来たが,回答してよいか。
従業員の不適切な行為によって会社が損書を被ったが,当該従業員に対して損害賠償等を請求することはできるか。
顧問契約について
顧問契約
顧問契約は,企業様,個人事業主様から,毎月一定の顧問料を頂戴する代わりに,日々の法律問題等について,迅速に相談を実施し,また,交渉等対応等の際に,弁護士費用等を一定額軽減するものです。
顧問契約は,企業様,個人事業主の方が主な対象となります。
顧問契約とその時々の法律相談の相違について
継続的な経済活動に伴って,種々法的な問題が生じることがあり,主には,従業員との関係,取引先等との関係等が多いかと思われます。
このような諸問題が起きた際、事後的に対応する側面が強いものを一般的な法律相談とすれば,顧問契約においては,継続的にお打合せやお付き合いをさせていただくことから,トラブルの端緒となりえそうなものを事前に察知し,紛争を防止しやすい機能があるものと言えます。
メリット,デメリットについて
法的紛争は,事後的に対処することの方が,解決までの時間,労力,費用等含めて負担が大きく,紛争が生じないように事前に予防することの方がメリットはあるものといえます。
他方で,一般的には,頻繁に何らかの問題が起きているわけではないことから,その都度の法律相談等で対応する方が,結果的には経済的なメリットが大きい場合もあろうかと存じます。
ご検討について
顧問契約を締結したほうがよいのか否かについては,各企業,個人事業主の方の実情に合わせてとなりますが,主には,行っている事業活動の内容,取引先の性質,関係,数,従業員の有無,人数,内容,法律問題が生じうる蓋然性等によろうかと考えております。
また,ご依頼者にとっても,弁護士にとっても,顧問契約は,継続的にお付き合いすることとなることからも,顧問契約といった継続的なかかわりが望ましいのかについてご検討いただく必要がありますし,最初は個別の法律相談等での対応をお勧めしております。
以上の過程を経て,顧問契約をご希望されるとした場合には,どのような関わりが想定され,どの程度の費用となるかについて,ご説明差し上げます。